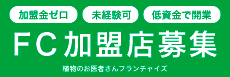水やりで差がつく!アルテシマを枯らさない湿度・水分管理法
黄緑の斑が映えるフィカス・アルテシマ。じつは「水やり」と「湿度管理」の精度でコンディションが大きく変わります。この記事では、枯らさないための実践ポイントを季節別・症状別にわかりやすく解説します。
―――
【1】アルテシマの“水”の基本思想
・基本は「乾いたらたっぷり」。常時湿らせっぱなしは根腐れの元
・鉢底から流れ出るまで与え、受け皿の水は必ず捨てる
・指で表土2〜3cmを触って乾きを確認(湿度計・水分計併用で精度UP)
―――
【2】季節別|正しい水やりリズム
● 春(発芽・展葉が増加)
表土が乾いたら“たっぷり”。新芽促進のためメリハリをつける
● 夏(蒸散MAX)
乾きが早い。朝の涼しい時間に。猛暑日は用土の乾き具合で“+α”を検討
● 秋(成長ブレーキ)
やや控えめへ移行。夜間の低温×過湿を避ける
● 冬(休眠気味)
回数を大幅に減らす。「完全に乾いて2〜3日後に少量」が目安。冷水はNG、室温の水で
―――
【3】湿度マネジメント(50〜60%が快適ゾーン)
・加湿器/濡れ軽石トレイで間接加湿
・朝の葉水で葉面のホコリ除去+蒸散をサポート(夜間の過度な葉水は冷え・病気のリスク)
・エアコン直風は乾燥と低温ストレスの同時発生要因。風向を外す or 位置をずらす
―――
【4】“過湿”と“水切れ”の見極め
■ 過湿サイン
下葉黄化→落葉/株元が常時湿って重い/用土が乾かない/カビ臭
▶ 対処:受け皿の水を捨てる→風を当てて乾燥→必要なら植え替え(腐根カット)
■ 水切れサイン
葉が垂れる・縁がカリカリ/葉面の艶が落ちる
▶ 対処:用土全体に行き渡るまで潅水→以後は“乾いたら与える”へリズム修正
―――
【5】用土・鉢で水分リスクを先回り
・推奨用土:観葉植物用土7+パーライト3(通気・排水を確保)
・鉢はプラ or 陶器の排水穴つき。鉢底石で目詰まり防止
・一回り大きい鉢への植え替えは1〜2年ごと(春〜初夏)…根詰まり=過湿リスク
―――
【6】“よかれ”が裏目に出るNG行動
・毎日ちょこちょこ与える(常湿化→根腐れ)
・夜の冷えた時間帯に潅水(低温×過湿)
・受け皿の水を溜めっぱなし(酸欠)
・急な置き場所変更で光量が激変(蒸散バランス崩壊)
―――
【7】症状別ミニフローチャート
1) 土の乾湿を指で確認
濡:風+時間で乾かす/受け皿水捨て/根黒変なら植え替え
乾:鉢底から流れるまで潅水
2) 葉の変化を観察
斑が薄い・徒長 → 光不足(補光 or 窓辺へ)
葉先枯れ → 乾燥 or 風直撃(加湿・風向調整)
3) 温度を測る
20〜30℃が理想/冬は10℃以上を死守
―――
【8】プロっぽく安定させる3つの習慣
・水やり前に“鉢の重さ”を持って比較(乾湿が体感でわかる)
・週1の葉拭きで気孔をクリアに(蒸散・光合成効率UP)
・温湿度計&光量計(スマホアプリでも可)で“勘”を数値化
―――
【まとめ】
アルテシマは「乾いたらたっぷり × 湿度50〜60% × 強すぎる直射回避」で安定します。
用土・鉢・置き場所を整え、季節ごとにリズムを微調整すれば、斑入り葉の発色も艶も見違えるはず。
今日から“与える量”ではなく“乾くリズム”を管理しましょう。